2024.05.13
#面白法人カヤック社長日記 No.132後任者(引き継がれた側)からみる事業承継あるある【面白法人のこれからの10年 #6】
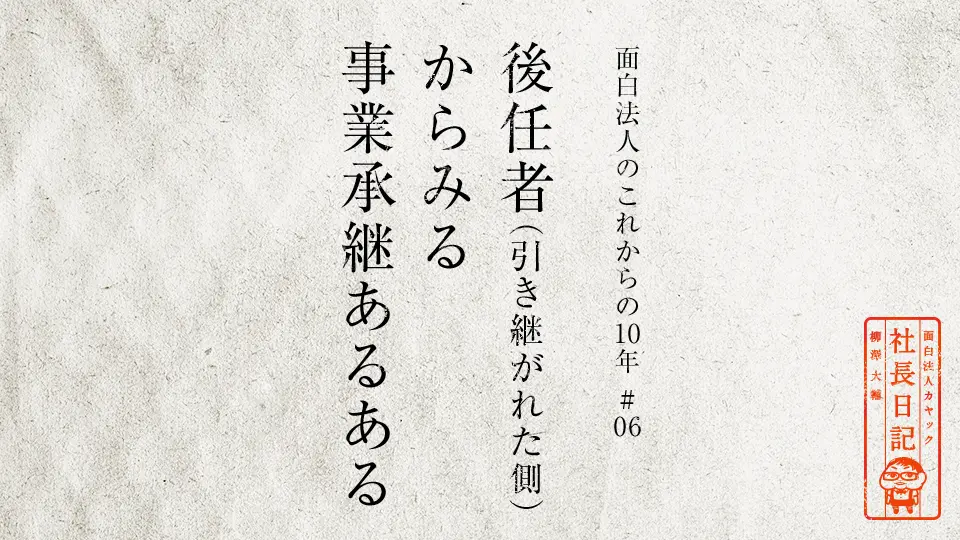
今回の社長日記は、僕(柳澤)ではなく、他の方からの寄稿文となります。
前回の社長日記の「カヤックの後継者育成計画」は、同じような課題を抱える経営者の中では好評だったようで、何人かの方からコメントをいただいたり、ディスカッションをさせていただくことができました。
その中の一人、「ビジョンプロセシング――ゴールセッティングの呪縛から脱却し『今、ここにある未来』を解き放つ」(英治出版)の著者で経営者の中土井さんとのやりとりは示唆に富んでいて得るものが多かったので、社長日記に掲載させてもらえないかと確認したところご快諾いただきました。
なので、中土井さんからのメッセージを少し編集して、寄稿という形で掲載させていただきます。
ーーーー
やなさわさんの社長日記「カヤックの後継者育成計画」を読ませていただき、インスピレーションを得ましたので、私は他の「後任者(引き継がれた側)」の人たちを見ていて、日頃から感じていることを書かせていただきたいと思っています。
後任者が囚われがちなメンタリティ
引き継がれた側の人たちの経営を創業経営者(前任者)と比べた際に、私が際立って共通していると感じるポイントは以下の2点です。
1.後任者は「会社をつぶしてはいけない」という囚われが強い
2.前任者からの入れ替わりの時の、ネガティブインパクトに対する前任者の胆力が成否を決める
まず 1. についてなのですが、創業経営者とサラリーマン経営者や2代目以降の間にある圧倒的な差のように見えています。
創業経営者は、いろんなリスクをとり、危機を乗り越えながら、会社を育ててきた経験があり、「会社を絶対につぶさない」というコミットがありながらも、腹がくくれているというか、「なんとかなるし、なんとかする」もっといえば「ダメならやり直せばいい」という修羅場経験に根差した独特の感覚があると思います。
それに対して、2代目以降は、経営における修羅場経験という意味で、創業経営者と比べてどうしても見劣りしてしまいます。そのため、「会社をつぶしてはいけない」という暗黙の前提とプレッシャーが生まれてしまい、自分自身の中で肥大化させてしまうようです。それが判断を鈍らせるというか、偏らせているように見えています。それでなくても、創業経営者と比べて自分はカリスマ性もなく、見劣りしているという引け目がある中で、前任者から引き継いだ時よりも、会社を潰すほどに悪化させてはいけないという感覚にいつの間にか支配されてしまうようです。もし、そんな状況にでもなったなら、「自分は落伍者だ」、「経営者として失格だ」、「私は無能だ」などど、自分自身を全否定してしまうことになるということを心のどこかで恐れているようにも見えます。
そんな風な色んな囚われが積み重なることで、一も二もなく会社をつぶしてはならないという強固な観念が生まれてしまうのではないかと思います。これが創業家による世襲の場合、3代目以降になると、より強くなるようにも感じています。
一方、ファンドに売却した場合は、個人の印象ですが、真逆にめちゃくちゃドライになることもあると思うので、上記のようなことは当てはまりづらくなります。ファンド系の後任者によっては、買収した会社に対して思い入れを感じていないようにみえることもあります。会社が伸びなくても、一時的に財務諸表を綺麗にして売却すればよいという発想になっているように見えるときもあります。
事業承継後に、前任者を襲う「返り咲き引力」と問われる胆力
次に 2. 「前任者の胆力による成否」についてですが、これは「事業承継失敗あるある」です。
後任者が就任した後、しばらくの間は、必ずと言っていいほど、人が辞めたり、業績も落ちたりします。ある意味、それは致し方のないことですし、前任者もそれは覚悟していたはずです。しかし、意外と前任者はそれに耐えられず、口を出したり、返り咲いたりするケースが多いようです。
耐えられず、介入する理由には様々にあると思いますが、代表的なものは以下のようなものかなと思います。
①業績が急激に悪化する
②人が大量に辞める
③前任者である自分に社員から「状況のひどさ」が立て続けに報告される
④将来に禍根を残すような変革施策を後任者が行ってしまう
⑤後任者が「押さえどころ」をことごとく見逃し、機会損失とリスクを増大させているように見えてしまう
全てが一度にそろえばもちろんインパクトはとりわけ大きいですが、1つだけでも十分に返り咲きのトリガーになったりします。
特に、②の人が大量に辞めるということに対しては、前任者は耐えられないものがあるようです。実際、会社の中でコア技術を持っている人であればあるほど、その人が抜けた穴はまず埋められず、会社としてのコアコンピテンシーを失うことを意味してしまいます。そうしたコア人材たちの離職が相次いだ時に、我慢して耐えて見守ることが難しくなるようです。このままでは取り返しがつかない事態へと悪化していくのではないか、と。
そうした悪い予測をさらに加速させるのが③です。単純に後任者の進め方が気に入らないだけだったとしても、社歴の長い社員ほど前任者に対して泣きつくように色々と相談したりするので、余計に前任者は妄想が膨らんでしまうだけでなく、薄々自分自身、不安に思っていたことが自分の想定を超える形で現実化してく感覚を強くさせてしまうようです。
④、⑤も似たような話で、後任者が手を出した施策の副作用は目に見えているのに、それが見えていないのではないか、軽視しているのではないか、肝心な押さえどころが全く見えていないくらい経営者としての大事なセンスが著しく欠けているのではないかと感じ、時間の問題で状況は良くなっていくだろうと楽観視できなくなるのだと思います。
以上の内容を踏まえて、前任者への教訓を考えてみますと
・後任者は、自分とは違う人間なので前任者が生み出してきたような結果や期待したような結果にはならない可能性が高いことを覚悟しておく必要がある
・前任者である自分が大事にし、積み上げてきたものが破壊され、踏みにじられるような出来事が起きたとしても、「後任者に譲った時点で、その会社に対して前任者である自分は口出しする権限は何もない」と腹をくくる
・継承後の口出しは、効果よりも副作用の方が大きくなる可能性が高いことを肝に銘じておく
これらは「成功を約束するもの」というよりも、「失敗を避けるための最低限押さえておくべきこと」と捉えていただいた方がよいかと思います。
「ノスタルジーと有能な後任者への嫉妬」という見えない罠を超える
一方で、様々な事業承継を見ている中で、結果的にうまくいっているケースを見ると、特に以下のような2つのパターンが際立って典型的だと感じています。
1.後任者が前任者と異なるタイプで滅茶苦茶優秀
2.会社が危機的状況になってからの後任者への引継ぎ
まず、1の「異質で優秀な後任者」への引継ぎについてです。
いくつか例があるとは思いますが、例えば、創業社長を超えて、はるかに会社を大きくした後任者が身近にいます。
事業承継という意味では、その後任者の才能を見抜いた前任者の功績は大きいのはもちろんのこと、自分とは異質なタイプを抜擢できたというのが一つの成功要因だったのではないかと考えています。
この会社のケースは、前任者は元々、アナログなサービスを主力事業とした会社を経営されていたそうなのですが、インターネットを主軸とした新しいビジネスを提案してきた後任者に対して、自分にはないものを持っていると思い、思い切り任せるだけでなく、自分は老害になるだけだと思って、身を引いたそうです。
ある意味、偶然の賜物というか、結果論に過ぎない部分もあるとは思います。ただ、見逃せないポイントは、異質な人材を登用できたことに加えて、「後任者の方が創業者である自分よりも会社を成長させていく上で有能である」という事実を受け入れ、自分自身が育ててきた「古き良き文化」へのノスタルジーを捨てられたかどうかにあります。
創業経営者にとって、自分が生み出した会社は、自分がお腹を痛めて産み、手塩にかけて育てた子どものようなものなので、でこぼこなところも含めて愛着があってもおかしくはありません。
例えば子どもが、自分以外の他の誰かの影響で愛着と思っていた部分が削り取られ、どんどん洗練されていったら。変化や成長を喜ぶ気持ちと、変わって欲しくなかったなという少し寂しい気持ちもあるのではないでしょうか。
会社経営の場合で考えると、後任者の手腕によって業績と引き換えに、会社の個性として残したかったこと、自分自身や周りからも愛着を持たれていた側面が削られていく感覚にもなるかもしれません。
また、実際にその手腕によって瞬く間に業績が伸びたりすると、自分の経営者としての能力の無さを見せつけられるような気持ちになる、すなわち嫉妬心のようなものが前任者に生まれることも十分にありえます。
そうしたことを乗り越えて、有能な後任者にバトンを渡せるのだとしたら、それは前任者の功績と言えるのではないかと思います。
次に、2「危機的状況下での引継ぎ」です。
このパターンも国内外を代表する企業で複数の例があると思っています。
危機的状況と言うのは、不祥事が起きて、前任者が辞任せざるを得なくなる、突然死するなどです。不祥事の場合で辞任しても、前任者が院政を引ける状態になっているものは省かれます。
これはある意味、準備なく引き継がれる形になるのですが、意外とハードランディングでありながらもうまくいったりします。もちろん、後任者の能力は一定以上必要です。
ただ、実は順風満杯な状態で会社を引き継ぐより、危機的状況の方が承継はうまくいくだろうなというのが私の見立てです。
なぜなら、周りは「火中の栗を拾ってくれた人」として認識するので、支えやすくなりますし、うまくいかないのが当たり前なので、後任者の能力不足が業績を悪化させたというインパクトが少なくて済むようです。すなわち、周りの後任者への期待値が低く設定されます。
「誰がやっても同じ」感は会社のバラバラ化を加速させづらいということなのだろうと思います。
加えて、後任者も元々、状況が悪化するのは目に見えていたことなので、「会社をつぶしてはいけない」という囚われから解放されやすいようにも見えます。
ここまでの整理を元にして、カヤックのことを考えてみると、やなさんが事前に事業承継していくことを社内外に発表されているというのは、ソフトランディング上は非常に有効かも知れないと思っています。
結局のところ、私は社員の中には、その時点でのトップと精神的な結びつきがある人は一定数いて、そうなるとトップが退任した時点でいなくなるというインパクトは避けられず、後任者と結びつきがある社員にそのうち入れ替わるということは、自然のリズムのように思えているからです。
その組織の新陳代謝はトップ交代においては避けられなく、突然事業承継してしまうと、会社の方が耐えられないような状況になるので、事前にオープンにしながら進めて行くというアプローチは良いチャレンジではないかと思われます。
ーーーー
以上です。
寄稿ありがとうございました。
今回寄稿いただいた中土井さんは、僕が1冊の本にまとめた「励ましのサイエンス」
https://www.kayac.com/news/2022/09/yanasawablogvol109
においても、総集編として励ましのサイエンスを一緒に対談しながらまとめて頂いた方です。いつも変わる御縁に心から感謝申し上げます。
中土井僚さんプロフィール
リーダーシッププロデューサー、組織変革ファシリテーター。「自分らしさとリーダーシップの統合と共創造(コ・クリエーション)の実現」をテーマに、マインドセット変革に主眼を置いたリーダーシップ開発及び組織開発支援を行う。
コーチング、グループファシリテーション、ワークショップリードなどの個人・チーム・組織の変容の手法を組み合わせ、経営者の意思決定支援、経営チームの一枚岩化、理念浸透、部門間対立の解消、新規事業の立上げなど人と組織にまつわる多種多様なテーマを手掛ける。
note : https://note.com/nakadoi/
6月に「ビジョンプロセシング――ゴールセッティングの呪縛から脱却し『今、ここにある未来』を解き放つ」(英治出版)を発売。
当日記の無断転載は禁じられておりません。大歓迎です。(転載元URLの明記をお願いいたします)
===
このブログが書籍になりました!

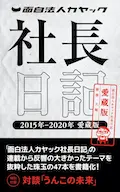
バックナンバー#面白法人カヤック社長日記
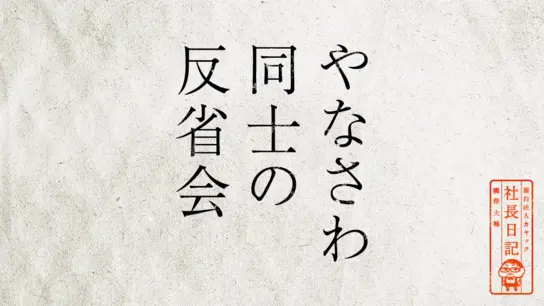
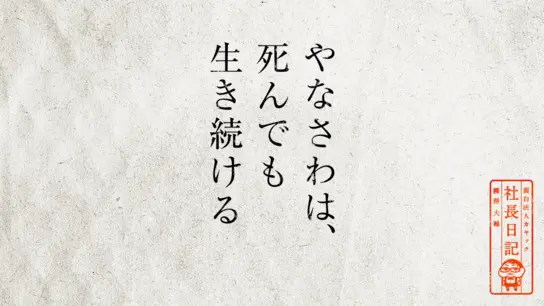
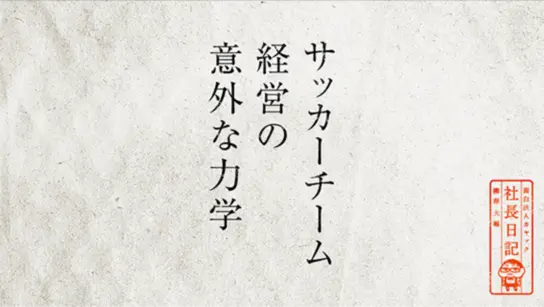
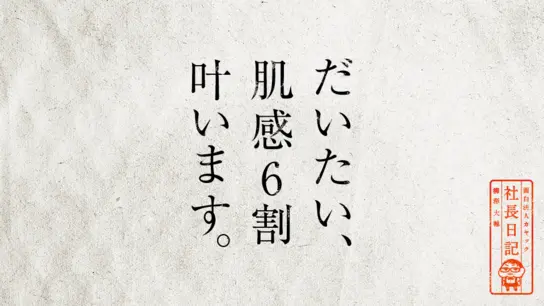
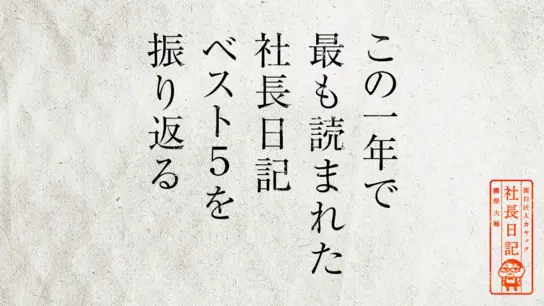
 Facebookページ
Facebookページ 公式X
公式X 代表柳澤のX
代表柳澤のX