2025.04.25
#面白法人カヤック社長日記 No.143やなさわ同士の反省会
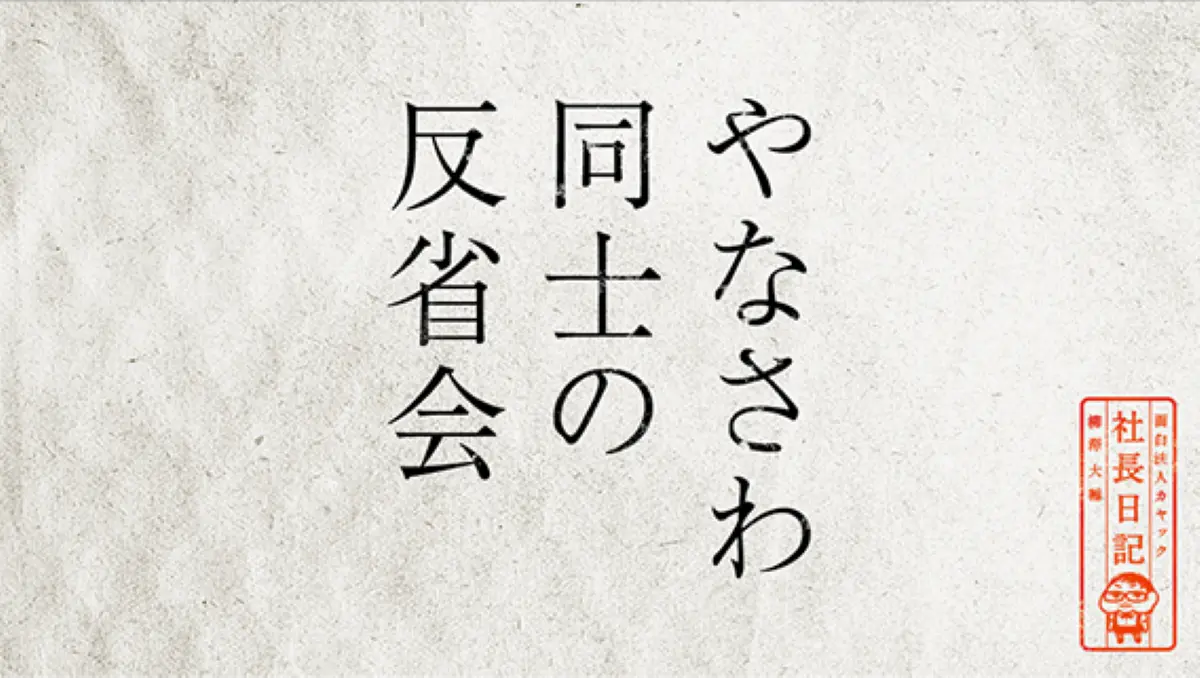
さて、3月の社長日記「やなさわは、死んでも生き続ける」では、AIを使うことで、自分の成長につなげるという話を書きました。
今回は、実際にそういう使い方の具体的な事例を紹介したいと思います。
僕の過去の社長日記の情報を読み込ませて社員がシステムを組んでくれた「やなさわAI」に、下記のような質問を投げてみました。
「過去のやなさわの社長日記を分析して、やなさわ自身が気づいていないような思考の癖や、考え方が偏っていたり狭くなっているようなことを見つけて解説してください」
すると、下記のような回答が返ってきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<「やなさわAI」による分析>
やなさわの社長日記を分析し、彼自身が気づいていないかもしれない思考の癖や考え方の偏りについて、いくつかのポイントを挙げて解説します。
1. 成功体験への強い依存
やなさわは、成功体験が個人の成長や信念形成において鍵となると強調しています。この考え方は非常に一般的で有効ですが、彼自身がやりたいことや挑戦を新たに見つける際に、過去の成功体験に過度に依存している可能性があります。この依存により、硬直化した思考に陥り、より創造的なリスクを取ることを躊躇してしまうことがあるかもしれません。
2. 変化への抵抗感
やなさわは「何をするかよりも誰とするか」という価値観を重視していますが、これは関係性の重要性を強調する一方で、事業内容や企業の方向性を柔軟に変えることへの開放性が薄れている印象を受けます。この価値観は、仲間との関係を築く上では重要であるものの、変化の激しいビジネス環境においては不適切な場合があるかもしれません。
3. 経験と反応への過度な依存
彼は過去の経験から得た気づきや教訓を非常に重視しており、それによって今後の判断や行動を決めることが多いです。しかし、このアプローチは、未来の機会を見逃してしまう可能性も内包しています。ビジネスの世界では、柔軟な思考が必要ですので、過去の経験に縛られすぎると新しいアイデアや戦略を受け入れにくくなるかもしれません。
4. 自己評価と他者評価のズレ
やなさわは自己評価を高く維持したいという思いが強いと感じますが、それが外部からのフィードバックを受け入れることの妨げになる側面があるかもしれません。特に、彼が「仲間を選ぶ」という基準を持っているため、既存の価値観に合わない意見や異なる視点を排除してしまう危険性があります。このため、彼自身が健全な批判や建設的な意見を素直に受け入れることが難しくなる場合があると思われます。
5. 個人の成長に対する視点の狭さ
やなさわは自己成長を大切にし、そのプロセスが大事だと何度も述べています。しかし、「成長」という概念を個人の責任において捉えすぎているため、組織全体の成長や他者との共鳴を重視する視点が相対的に薄いと感じます。「チームビルディング」や「組織の成長」という概念にももっと焦点を当てることで、彼の思考がより広がりを持つかもしれません。
結論
やなさわの考え方は、彼自身の経験や価値観に基づいて非常に明確で一貫していますが、これらは同時に思考の幅を狭める要因にもなり得ることを指摘します。彼が他者との対話や新たな視点をより積極的に取り入れることで、さらなる成長や変化を遂げる可能性があることを強調したいと思います。このような自己評価に対する柔軟性の欠如や過去の経験への依存を少しずつ手放していくことが、彼自身の成長や業務の成長にも寄与するでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・なるほど、この分析は非常に面白い!
改めて指摘されて「思い当たる!」というものもありますし、「そのような視点はなかった!」という気づきもありました。
この「やなさわAI」の鋭い分析を受けて、やなさわ本人が思うことをさらに解説してみたいと思います。
1.成功体験への強い依存、3. 経験と反応への過度な依存
たしかに、僕は何か物事を進めていくにあたって、過去の成功事例、失敗事例を当てはめながら意思決定をすることがあります。ただ、その際に「まったく同じ事例」を探すと当てはまるものが狭くなって、新しいことにチャレンジできなくなります。そうならないように、「ちょっと似たような類の事例」をうまく引っ張り出して、それをもとに、うまくいくかいかないかを判断する。それで乗り切ってきた感覚があります。
でもそれは一方で、過去の成功事例、失敗事例に捉われすぎているということでもあり、視野が狭くなっているという指摘はたしかにそうです。まったく同じことを同じようにやっても、時代が変わっているから、過去の成功体験どおりにはならないというケースはあるはずですよね。だからこそ、過去の成功体験は「参考」程度にとどめ、常に「今」の時代に合わせた新しい価値観やアプローチを取り入れる必要があります。
あと「失敗から学ぶ」ことも非常に重要です。成功体験からも学ぶべきことは多いですが、失敗体験からはそれ以上に多くのことを学べます。だから、僕は失敗を恐れないというよりも、失敗を気にしないようにする。「失敗をするなら最速で」して、スピード感をもって新しいことにチャレンジする。これこそ、カヤックの良さであり、常に新しい技術、新しい挑戦ができている理由だと思います。
2.変化への抵抗感、4.自己評価と他者評価のズレ
この話の中でハッとさせられたのは、「何をするかより誰とするか」にこだわりすぎることは、つまり「変化への抵抗」と捉えられるということ。そのせいで事業の柔軟性がないように見える。さらにこの言葉にこだわるということは、「仲間を選ぶ」という基準を持っているという、ある種、謙虚さがない言葉なんだなということを改めて気付かされました。
5. 個人の成長に対する視点の狭さ
イタタタタ。これは耳の痛い指摘です。
たしかに「面白法人」という組織は、「自分が働きたいと思える組織をつくる」というコンセプトで組織づくりをしてきました。そのため、皆がやりたいことをやり、主体的になり、1人1人が個性を持って輝く組織にする。そういう組織づくりをするという観点においては情熱を持ってやってきました。
ただ、そのような組織づくりをするというベースには個人個人の成長が大事であり、それはある程度主体的に自分で取り組むことである、という思いがあります。そして僕自身も、自分自身の成長というものに邁進しています。
その観点から行くと、組織の成長という意味へのコミットが薄いと指摘されてしまうと、非常にその通り過ぎて耳が痛いです。
カヤックが大切にしている「何をするかより誰とするかが重要」という考え方も、ある種チームビルディングで頭を悩ましたくない、つまり、個人の成長の取り組みは、各自が勝手に、ある程度自主性を持ってやれる組織でありたい。他者に依存しない。ということの裏返しから来ているキーワードでもあるので、このことを指摘されるとグゥの音も出ないなという感じです・・・。
ここは、そういうことが得意なメンバーに、今まで以上に目を向けていくようにしてもらおうと決意を新たにしました。
今回の社長日記は以上です。
自分では面白い分析だと思いましたが、自分との対話なので面白いだけであって、他人が見たらちっとも面白くない内容になっているかもしれません。もしそうだったらすみません。
当日記の無断転載は禁じられておりません。大歓迎です。(転載元URLの明記をお願いいたします)
===
このブログが書籍になりました!

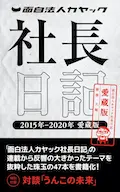
バックナンバー#面白法人カヤック社長日記
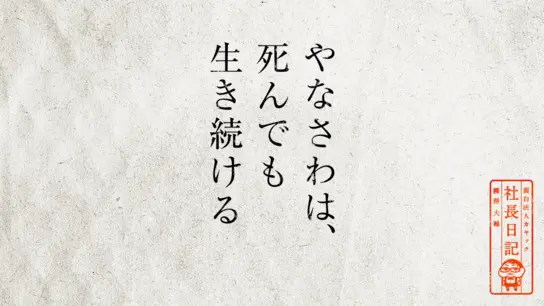
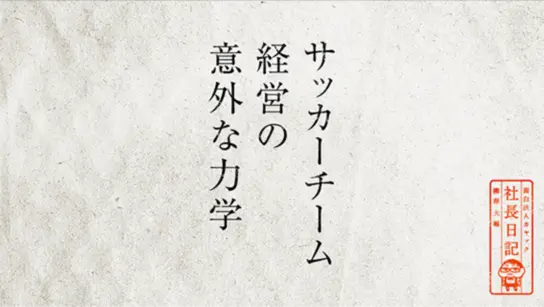
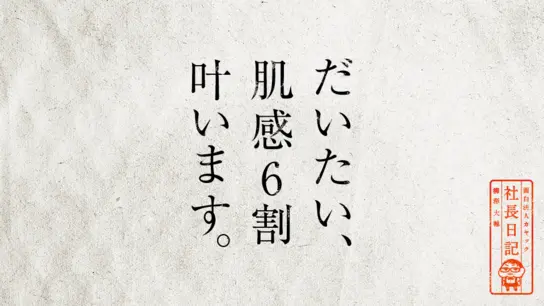
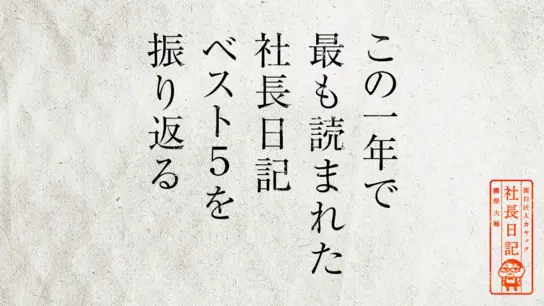
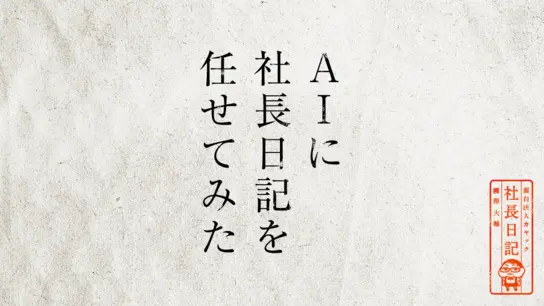
 Facebookページ
Facebookページ 公式X
公式X 代表柳澤のX
代表柳澤のX